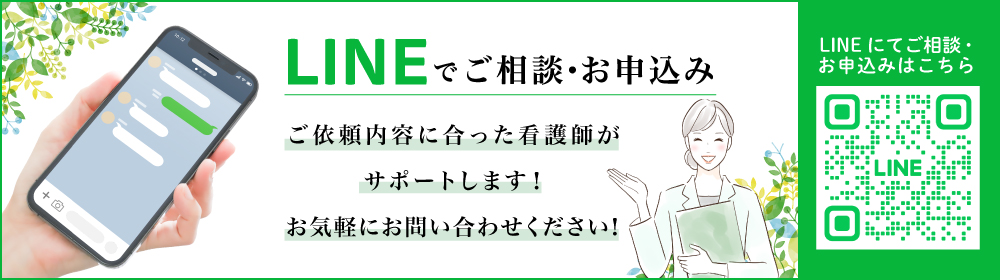「介護」と聞くと「大変そう」という印象を持つ方が多いと思いますし、実際に介護対象者を身内で支えるのは簡単なことではないことから、家族全員の暮らしを保つためにもプライベートケアを依頼される方は多くいらっしゃいます。この記事では、介護職のプライベートケアの上手な利用方法や費用相場についてご紹介していきます。

介護職ならではのプライベートケアの特色
まず、介護職とは、高齢者や介護を必要とする人が、その人らしく生活を過ごせるようにサポートをする専門職のことです。
そんな専門職によるプライベートケアの特色としては、介護保険でできないことでも利用者や家族の希望にそったオーダーメイドの生活支援サービスを提供してくれるところです。
また、プライベートケアは利用者の年齢制限がないところも特色といえるでしょう。
介護の知識をもつ専門職であるからこそ、利用者それぞれの状態にあった適切な対応ができるので、家族では支えるのが難しい在宅面を安心してまかせられます。
最近は介護職のプライベートケアの需要が高まっており、要介護や要介助の認定がされなくても日常生活を送る上で「サポートしてもらいたい」方やや保険適用のケアを受けていても「やって欲しいケアがある」からとプライベートケアを併用する方が多くなっています。
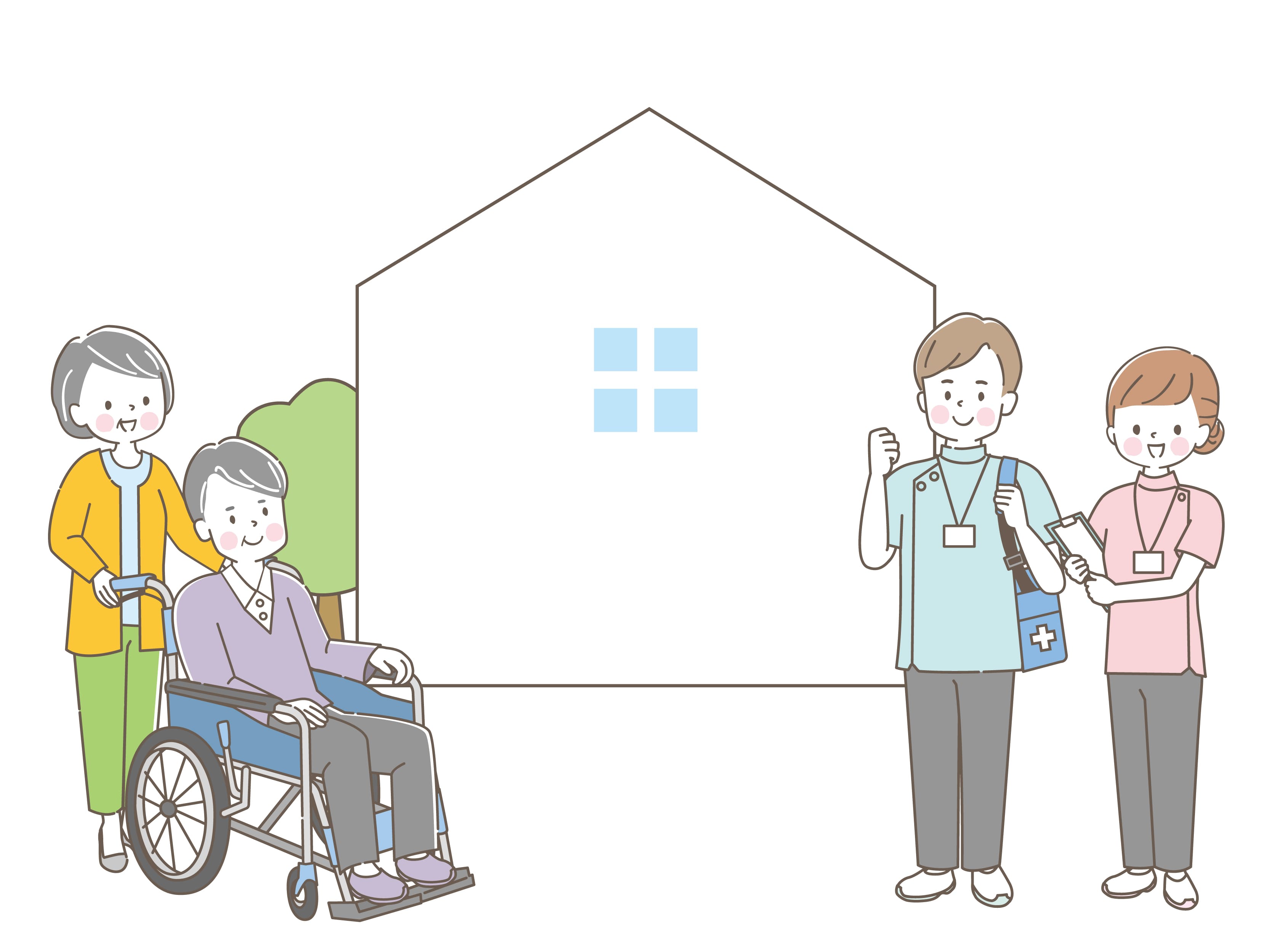
介護職によるプライベートケアのメニュー
介護職によるプライベートケアのメニューには、介護を知らない方からすると「習い事の付き添い」や「草むしり」、「洗濯」、「窓ふき」や「洗車」というような「それもサービスとして提供しているの?」というようなメニューもありますが、しなくても生活はできるけれど利用者本人や家族が「することで暮らしを楽しくできる」ケアが充実しています。
例えば、プライベートケアには次のようなものが含まれています。
・食事、入浴、排せつ、着替え等の介助
・歯磨きや入れ歯洗浄などの口腔ケア
・通院、散歩、習い事、買い物など外出の付き添い
・洗濯や掃除、ゴミ出しや家事などの代行
・ペットの世話
・話し相手
・書類の整理や契約書の記入などの手伝い
・来客へお茶出しや食事の提供などの対応
・家の修理や家具の移動
・電話による相談
・長時間の旅行の付き添い
・冠婚葬祭やお墓参りの付き添い
・体調管理の声掛け
・妊娠中や産後のお手伝い
このように、メニューの幅広さが魅力のプライベートケアですが、依頼するところによって対応しているメニューや料金が若干異なりますので、利用したいケアについて対応可能か事前に確認することをお勧めします。
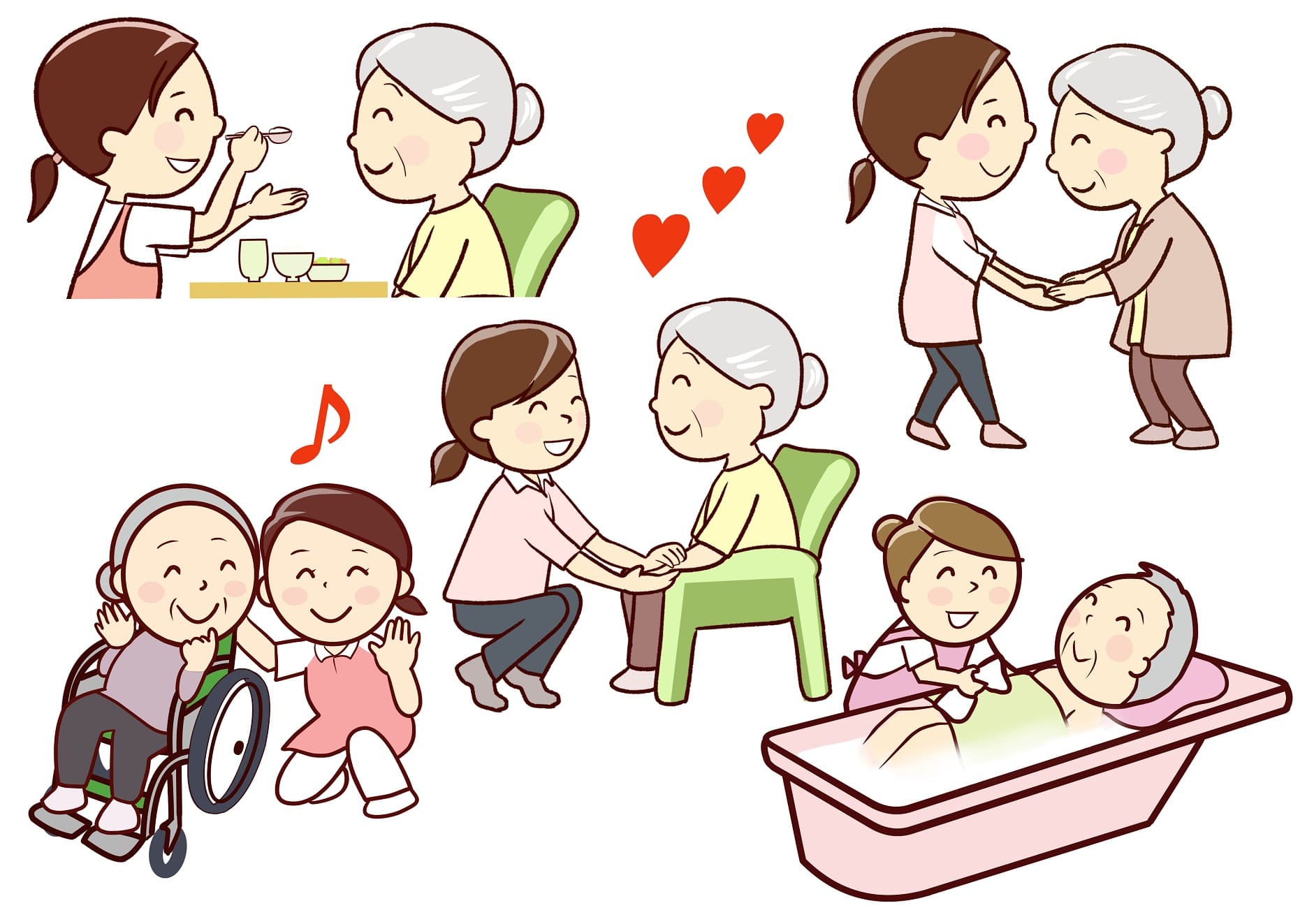
プライベートケアを提供する介護職の種類
介護職は無資格や未経験でも働ける仕事ですが、手厚いサービスを望む利用者が増えていることから、資格をもったスタッフによるプライベートケアが支持されています。
では、在宅などでプライベートケアを行う介護職の種類について、代表的な職をご紹介していきましょう。
・訪問介護員(ホームヘルパー)
高齢者や障害のある方々への食事・入浴・排泄・移動などの介助を行います。支援につながる買い物や掃除、洗濯などの生活介助も行います。
介護職員として基本的な知識やケアを身につけていると証明できる介護職員初任者研修(ヘルパー2級)の資格やより介護の知識や技術を提供できる介護福祉士実務者研修(ヘルパー1級)の資格があります。
・介護福祉士(国家資格取得及び登録が必要)
高齢者や障害のある方々への専門的な知識をもとに食事・入浴・排泄・移動などの介助を行います。支援につながる買い物や掃除、洗濯などの生活介助も行います。
さらに、介護の現場のリーダー的存在として、介護者への指導やアドバイスなども担います。
ただし、医療行為にあたるケアは基本的に行えません。
・社会福祉士(国家資格取得及び登録が必要)
高齢者や障害のある方、日常生活でサポートが必要な方々へ専門的な知識を活かして相談にのったり、問題に対する解決策の提案などの支援を行います。
職場によっては、ソーシャルワーカーと呼ばれていることもあります。
ちなみに、看護師は医師の指示のもと医療ケアを行えるため医療職となります。
そのため、介護の現場では医療措置を必要とする利用者が多いことから、介護職によるプライベートケアの内容を含む看護師によるプライベートケアは「医療ケアもまかせられる」と注目度の高いサービスです。
他の介護職としては、生活相談員や支援相談員、福祉用具専門相談員、介護事務、介護ドライバーなど、このように介護の現場では人々が協力し合って利用者を支えています。

プライベートケアは誰でも受けられる?
介護保険が適用されるケアには対象年齢による制限がありますが、プライベートケアは年齢制限がなく乳幼児から高齢者まで誰でも受けられるサービスとして提供されています。
ただし、医療行為にあたるケアは資格が必要となるため、すぐには対応できない会社もあります。そのため、医療器具を扱う必要がある方や持病やケガの心配がある方々は看護師によるプライベートケアが安心できるでしょう。

プライベートケアの費用相場
誰もが利用できるプライベートケアは、保険適用外サービスのため自費(自己負担)となります。
気になる費用については、医療ケアも可能なサービス内容かどうかで利用料金が変わりますが、おおまかな費用相場を見ていきましょう。
・入会金や登録料
無料~10万円程度。
提供サービスの内容によって料金設定が異なるので「どんなことまで可能か」など事前確認をすると良いでしょう。
・1時間当たりの基本料金
3,000円~10,000円程度。
医療行為ありのケアは料金が高めになります。
また、「2時間から利用可能」など、利用者が自由に時間を決められない場合もあるので確認が必要です。
・早朝や深夜の加算料金
基本料金の25~50%増し程度。
土日祝日や年末年始の利用の場合、基本料金に加算されることもあります。
選ぶ際のポイントとしては、全額自己負担になるため利用料金の値段設定に目が行きがちですが、他より安いと思っても希望のケアが基本料金のサービスに含まれていなくて追加の料金が必要だったり、対応していないこともあります。
特に身体に不調をかかえる方や医療ケアが必要な方、今後医療ケアが必要になりそうな方は看護師によるプライベートケアの方がメニューの自由度が高い場合もあります。料金も結局同じような額になるという話もよく聞きますので、詳細な見積もりを確認してからの契約をおすすめします。

プライベートケアに利用手続きはある?
利用者本人の状態によってケアの内容も変わるので、プライベートケアに利用手続きはあります。
初めて利用する場合は「家の中のことを知られたくない」や「外に家の事情がもれないか心配」という抵抗感もあると思いますが、介護ケア法によって、介護に従事する者は利用者本人や家族の氏名や住所、家族構成、健康状態や精神状態、利用している介護サービス名などのプライバシーを第三者に開示してはならないと定められています。
このように守秘義務で生活や情報が守られますので、安心して契約できます。
契約までのメールや電話での相談や問い合わせ、見積もりの提示などは無料のところがほとんどなので、気になるサービスは問い合わせてみることをおすすめします。

プライベートケアのより上手な使い方
では、実際にどのような利用がされているのか、プライベートケアの上手な使い方をご紹介していきます。
使い方① 服薬管理サポートを利用する
薬は人それぞれの状態によって処方されますし、説明があっても専門的な知識がないと、「症状が落ち着いたら飲まなくて良いといわれたけれど…」や「今日は飲んだ方がいいのか…」など不安になりやすいです。
そのため、残薬の確認、薬の飲み忘れや過剰に飲んでいないか、食事との相性は大丈夫かなど、毎日の服薬だからこそ専門の知識をもった看護師や介護者に服薬ケアを依頼することで利用者や家族の「大丈夫かな」という不安を解消できます。
使い方② 食事や入浴、排泄などの生活介助のサポートを利用する
家族といっても入浴や排泄を毎回行うことは体力面でも精神面でも負担となりやすいです。
また、「自分でできないことはないけれど、思うように排泄できない」といった利用者の場合、排泄は日々のことなのでストレスがたまります。
家族が排泄サポートをおこなって傷つけてしまい、さらなるケアが必要となることもあります。夜だけや朝と夜など、利用者や家族のタイミングの良い時に利用できるのがプライベートケアの利点です。
使い方③ 付き添いサポートを利用する
散歩をしたい、孫の発表会に行きたい、習い事に行きたい、買い物に自分で行きたい、旅行に行きたい等、「1人だと行けない」や「連れて行ってあげたいけれど病状が悪化したらと思うとできない」など心配から行動できない外出について、プライベートケアを利用することで願いを叶えることができます。
他にも、寝たきりになりやすい利用者のじょく瘡ケア、たんの吸引ケア、人工呼吸器のケアや胃瘻のケアなど、それぞれの希望にあったサービスを組み合わせられるので、利用者や家族の生活に安心感がうまれます。
※医療行為にあたるケアが看護師ならではのサポートになります。

後悔しないプライベートケアの選び方
自己負担となるプライベートケアですが「ケアして欲しい時間帯に来てくれて、希望通りのサービスをしてくれる」ことから、利用者は年々増えています。
プライベートケアを提供している会社も増えているため、利用する際は希望にあったサービスが提供してもらえるかを選ぶ必要があります。例えば、情報として提示されている料金だけで決めてしまうと「そのサービスは追加の料金が必要です」や「医療ケアはすぐには行えません」など、後からいくつもの手続きや加算費用が必要になる場合があります。
専属の人が付くのか毎回違う人が来るのかなど、実際に利用しようと決めてスタッフと相談していくうちに、気になることがどんどんでてくると思います。
「結局高いからと利用しなかった手厚いサービスの会社と同じぐらいの料金だった」と後悔しないためにも、契約をする前に利用者本人の状態を見てもらうことや希望条件を伝えること、きちんとした見積もりをだしてもらうことが必要です。特に、医療ケアを希望する方は看護師によるプライベートケアの問い合わせをすることをおすすめします。
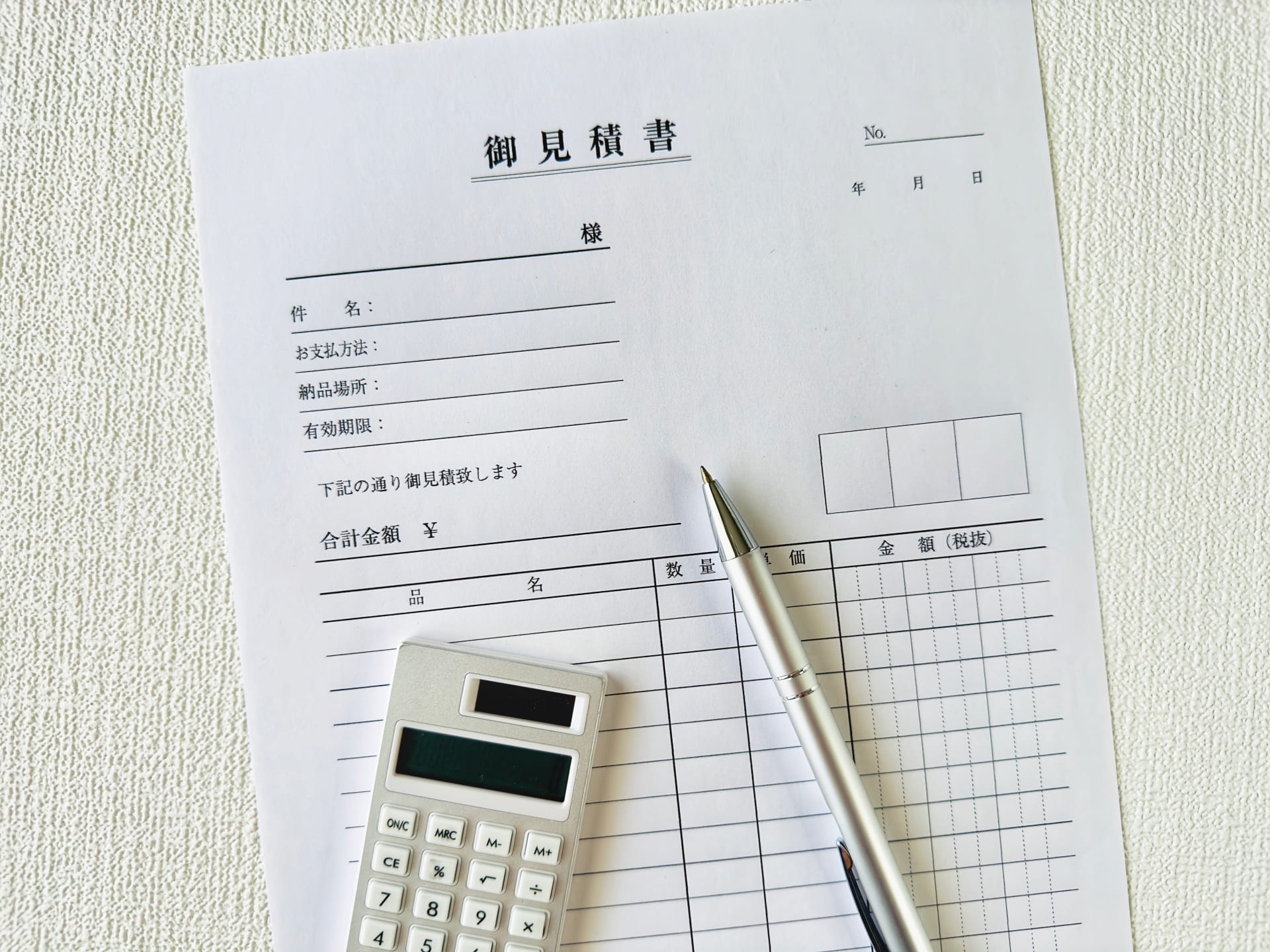
プライベートケアでトラブルが発生した場合の対処法
最後に、利用している際のトラブルが発生した場合の対処法について、いくつかご紹介していきます。
① 担当者を変えたい
担当者とは相性があって当たり前なので、その旨を契約したサービス会社に伝えましょう。
② 高齢者や家族が抱える悩み・不安を電話で相談したい
1. シルバー110番に相談する。
別名、高齢者総合相談センターといいます。都道府県ごとに設置されており、「シルバー110番+都道府県名」の検索で電話番号がわかります。検索できない場合は「#0808」に電話をして「シルバー110番につないで欲しい」と伝えるとつないでもらえます。相談料は無料ですが、通話料がかかります。
匿名での相談も可能なので、プライバシーは保護されます。
センターの相談員が対応できるもの以外の専門的なことについては、医師や弁護士、税理士など専門家が相談に応えてくれることもあるので、幅広い悩みや相談に対応してくれます。
2.地域包括支援センターに相談する。
介護や福祉、保健や医療の側面から総合的に相談することができる機関です。センターには、看護師、保健師、ケアマネージャー、社会福祉士などの相談に対応できるスタッフが所属しています。
センターに行けない場合は、職員に訪問してもらうことも可能です。「どうしたらよいかわからない」という思いも相談できるので、安心して問い合わせてください。

健康な人からすると「付き添いは自分達でできるのでは?」と思う方もいますが、身体が不自由になったり介護が必要となった時、「一定の時間でも専門スタッフにまかせられる時間」があると支える家族の負担が減りますし、利用者本人も第三者との交流によって暮らしが楽しくなることにつながります。介護による疲労が蓄積される前に、利用者や家族の状況にあったプライベートケアをぜひ検討してみてはいかがでしょうか。